
藤次郎は、なぜ世界の「TOJIRO」になったのか。
切れ味が良いとされる包丁を店頭で見かけても、実際にその質の良さを実感できる場所はない。知らない人は、知らないままだ。
一方、そうした「上等」な包丁を手にするために、時間がかかってもその一本を心待ちにする人たちもいる。その中には、言わずもがな、一般の主婦の方の姿さえある。さらには、国外メーカーからの熱烈なオファーもある。

珠玉の一本を作る「藤次郎」とは、何者なのか。いったいどのような歴史をたどり、世界に誇るブランド力を築いたのか。新潟県燕市の、藤次郎の包丁づくりと職人魂とを追いかける。
世界各国に広まり続ける「TOJIRO」
その答えを探しに、燕三条に工房を構える「藤次郎」へ。今や包丁は、スーパーや100円ショップなどでも手に入る。にも関わらず、藤次郎の包丁は、在庫切れになるほど大きな支持を得て、どんなに時間をかけてでも我が物にしようとする人もいる。彼ら、彼女たちは何に惹かれているのだろう。
海外では「TOJIRO」として親しまれるキッチンナイフは、アジアを中心に、北欧やアメリカなど、さまざまな国にその名を馳せている。
広く支持される大きな理由のひとつには、抜群の「切れ味」が挙げられる。

包丁に求められるのは、よく切れることはもちろん、その切れ味によって食材に味を染み込ませたりする効果や、口当たりを変化させたりすることもある。その点で、藤次郎の包丁は、世界各国のメーカーと比較しても、頭一つ抜きん出ている。
よく切れることを基本に、切れ味の持続力も高く、刃こぼれもしにくい。丈夫でありながら、素材の繊維をしなやかに切ることのできる藤次郎の包丁の特徴だ。
実際、藤次郎の売上の約半分は、海外からの注文だ。訪日外国人の購入数が国内販売数に含まれることから、ユーザーは国外居住者に多い。
なぜ、世界に名を知られる包丁メーカーになったのか。そこに至るまでの戦略はあったのだろうか。

農具メーカーが包丁づくりを始めるまで
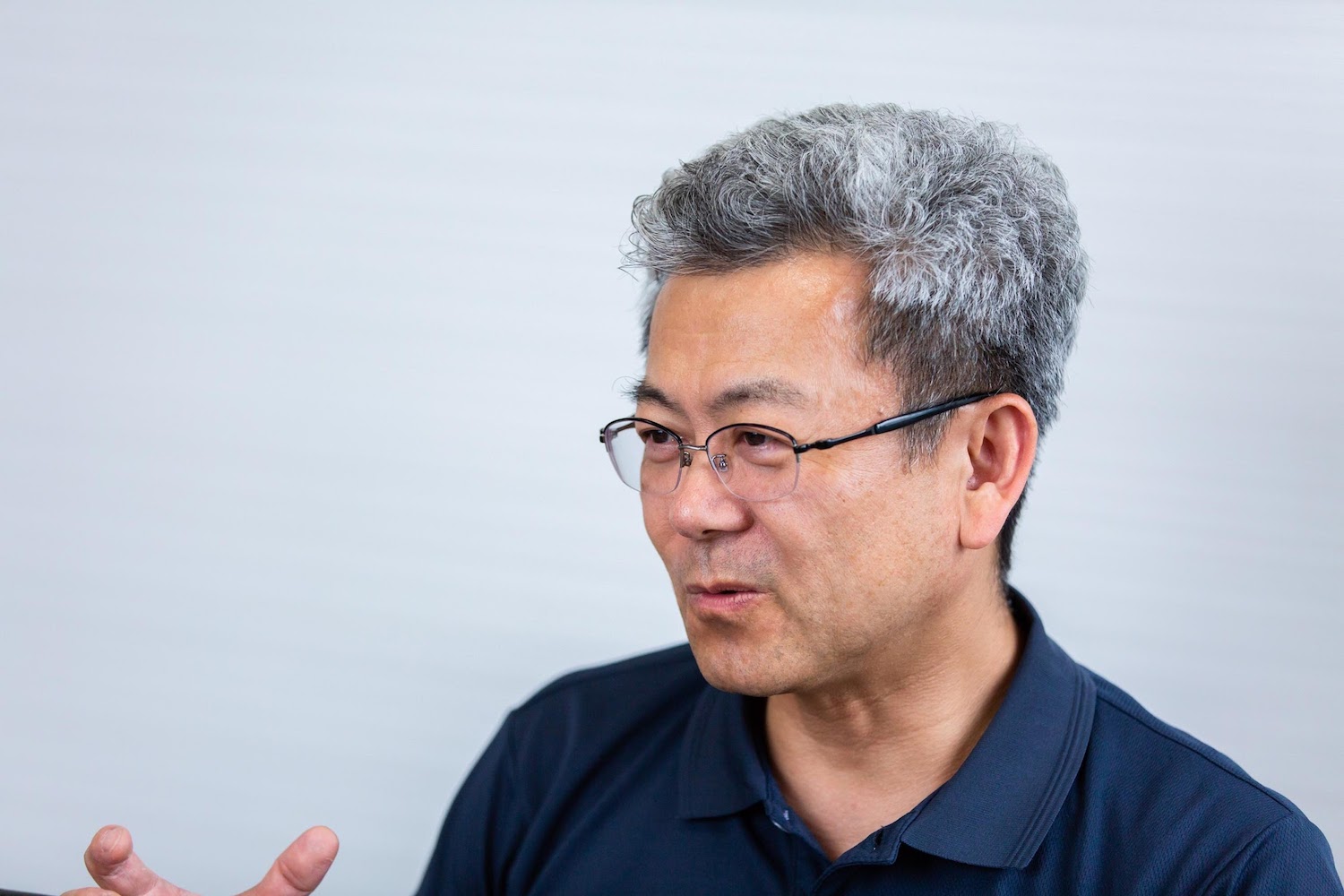
「先代の実家は、もともと農家でした。農家の多い地域だったので、農具メーカーとして生計を立てる家も多く、先代もその波に乗ったひとつです。ただ、農具メーカーには大きな落とし穴が。それは、農作業のできない冬の収入が、ほとんど得られないことです」
農家の1年間は、春から秋までが繁忙期、冬が閑散期となる。秋までに収穫した食料を少しずつ備蓄して、厳しい冬を乗り越える。ところが、農具メーカーは、そうはいかない。自らの手で食品を蓄えることができない分、冬にもメーカーとしての知恵を活かし、なにかを作って食べていく必要があった。
「近隣の農具メーカーが倒産する様子を目の当たりにし、なにか手を打たなければと考えたそうです。そこで出てきたのが洋食器の生産です。当時、燕三条で生産が拡大していた洋食器なら、農具づくりの知見を活かしながら、ニーズを汲んだ製品作りができると踏んだのです」

そうして、農具メーカーであると同時に洋食器メーカーとして、のれんを掲げ直した。すると、フルーツナイフをはじめとする刃物の需要が急拡大し、現在のような包丁一本に注力することになった。売上が急拡大したのは、2004年2月。きっかけは、ドイツ・フランクフルトで毎年開催されている世界最大の国際見本市「アンビエンテ」への初出展だ。
「国内のシェアだけでは、今後厳しくなる時代がやってくると考え、グローバル進出に挑みました。国内では当時、プチプライスの調理器具ブームが到来したことから、時短料理を提案する声も多く、包丁いらずのメニューが家庭で重宝されていったんです。その余波から、お金をきちんと支払って、質の高い包丁を手にするお客様が減っているように感じました」

「侍が持っている刀の切れ味が、あまりにも優秀であると絶賛されていたのです。そして、日本の刃物はとても優れている、と。海外では、国内でブームとなったプチプライスへの関心は薄く、良いものを使いたいと考える人々の方が多かったんです。そのタイミングで、2004年の『アンビエンテ』への出展が実現しました。本当に、時代が後押しをしてくれたと感じます」

「出展した包丁は、当社の中でも高級ラインのものでした。大量生産を行うことでコストを下げる作り方もできるのですが、こだわり抜いた品質を届けたいと考える私たちは、職人の手で1本ずつ作った製品を海外に持っていったんです。おそらく、そのチョイスが良かったのでしょうね。質へのこだわりをしっかりと伝えられたからこそ、あのとき藤次郎はたしかなブランドを確立できたのだと思います」
誠実にこだわり抜いた質、誰よりも早い海外展開、そして、時流に乗ったこと。偶然と必然が交差し、急成長を遂げる足がかりを得る。

数字にならない「切れ味」を追求する国、日本
ところで、包丁の切れ味とは、どのような基準で決まっているものなのだろう。数値で評価されるものなのだろうか。職人の目によって選出されていくものなのだろうか。その答えは実はどちらでもない。
答えを教えてくれたのは、工場の中を案内してくれた小川眞登(おがわ・まさと)さんだ。

国際的な指標として、機械に挟んだ厚い紙を同じ包丁で何度も切る方法が採用されていますが、あくまでも切れ味や耐久性は指標のひとつ。客観的な数値を基準に、なんらかの製品が優れていると決めることは難しいとされています」
使う人の手に評価が委ねられる。それが、包丁づくりの面白さであり、難しさなのだ。しかし、指標はさまざまと言いながらも、日本の刃物に対する評価が高いのは揺るがない事実である。

ところが、日本の刃物はそうはいかない。小柄な日本人が敵と戦うためには、身体的なハンデを刀でカバーしなければなりません。だから、日本の刃物は、どの国よりも切れ味の良いものへと進化を遂げたんです」
包丁の精度を知る、絶対的な基準は無い。
それでも、刀をはじめとしたこの国の刃物が、世界に誇れる様な品質であることは事実のようだ。
人の手だけが知る、数値化不可能な心地よさ
ここで、藤次郎の包丁づくりの工程を解説する。
1.プレス・ロール
金属板を包丁の形にくり抜き、ゆがみを取る。すき間がないようにくり抜くことで、廃材を極力減らす
2.焼入れ
プレスした金属に熱を入れることで硬度を増す
3.焼戻し
焼入れただけでは、硬度が高すぎてしまうため、再び熱を入れることで金属に粘りを増す。焼戻しを行うことで、しなやかな包丁ができあがる
4.研削
焼入れした金属を削り、包丁の本来の形に整える。複数回にわたって削ることで、なめらかなカーブを描き、切れ味を良くする

形を整えた金属を磨く。また、完成した包丁に入っている罫線のような細かい傷を付け、作業後の傷を目立たなくさせる

包丁に刻印を入れる。レーザーや職人の手彫りなど、製品のシリーズによって作業方法が異なる

包丁の切れ味を司る重要な工程。刃の研ぎ具合を調節する。製品ごとに微妙な個体差があるため、必ず職人が手作業で仕上げる
8.柄入れ
ハンドル(柄)を取り付ける
9.柄磨き
最終工程。出荷できる状態になるよう、ハンドルを調節し磨きをかける。オールステンレスの包丁であれば、磨くだけではなく、滑り止め(ショットブラスト)加工も行う
工場内では、刃物の鍛造から全てを人の手で行う打ち刃物と、機械をうまく使い価格を下げながら高品質な包丁を量産するための抜き刃物に分かれている。
「当社では、大きく2種類の製法で包丁を製造しています。打ち刃物は海外を中心に人気を誇る高級ライン。抜き刃物は量産型のラインでもっとも流通の多いシリーズを中心に、機械を一部で使用しています」
そうは言っても、全ての工程は人の手が品質を左右する。機械は人が使うわけだし、仕上がりのチェックをするのもまた人の目だ。

効率を上げるための機械と、それを操り質を担保する職人とがほどよいバランスで交わり、世界で太鼓判が押される藤次郎の包丁は生み出される。
世界の「TOJIRO」が日本の「藤次郎」として、母国でも愛され続けるために
しかし、信頼が積み重なった今でも、まだまだ慢心することはない。むしろ、藤田さんは現状を「まだ発展途上」と語る。

先ほど見学した工場は、創業50年を機にオープンファクトリーとして一般開放を始めた。工場のリアルな香りや雰囲気をまるごと感じてもらうための施設にしたいと、職人と直接話もできる空間が設けられている。

そのほか、ショップやショールームを併設したナイフギャラリーもオープン。藤次郎のすべてを知るための場所が、続々と世間に開かれていく。

言葉や意思だけではなく、認知度や親密度を高めるために実際に動いて産地を引っ張る藤次郎。ますますそのブランド力は盤石の基盤となるだろう。今後は全国的なアンテナショップの開設、ECでの直販、食に関する講座、製品のアフターケアなど、販路の拡大のみならず、包丁の使われるシーンにまつわる体験の提供もする見込みだ。
「世界各国から寄せられる日本の刃物への信頼は、今なお上がり続けているように思います。当社の売上のシェアも約半分は海外です。それ自体はもちろん嬉しいことなのですが、できたら国内の方にもっと藤次郎の包丁を届けていきたいと思っています。
日本のものづくりを、日本人が知らないなんて、なんだか悲しいじゃないですか。だから、そのためにできることを、ひとつずつすくい上げて、発信を続けていかなければいけないと感じています。
アンテナショップでは国内のさまざまな場所で製品を販売しますし、ECでは国内外のお客様へいつでも製品をお届けできるように体制を整えています。講座では食そのものに興味を持ってくださる母数を増やしたいですし、アフターケアの徹底によって藤次郎の信用力をさらに底上げしたいですね」

最後に、質問を投げかけた。
──産地としての燕三条という土地を、これから先、どのように育てたいと思っていますか?
「しなやかな地域になってほしいと思っています。自分たちの儲けばかりを考えるのではなく、一人ひとりが地域のためを想いながら、ものづくりができる場所。そうなっていったら、燕三条のものづくりはもっと広がりを見せるのではないでしょうか」
朗らかな藤田さんの表情から、未来への期待が感じ取れた。

さらには、その実力の上にさまざまな複合的な要素が重なり、ブランドの信頼感が醸成されることとなる。藤次郎の歩んできた道のりは平坦な道ではなかった。彼らは事業が立ち行かないやるせなさも知っている。その弱さを知るからこそ、現状に奢ることはない。
そうした一切の思いを抱き、今日も一本と誠実に向き合う。そしてこれからも燕三条の土地とともに、強くしなやかにはるか遠くの誰かのもとで道具の魅力を届けるのだろう。
〒959-1277 新潟県燕市物流センター1丁目13番地
TEL:0256-63-7151
FAX:0256-64-3811
https://tojiro.net/



