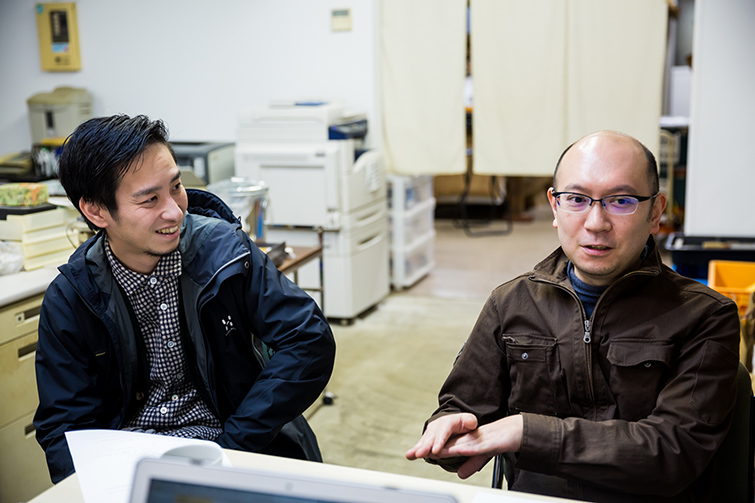包丁の消費文化を塗り替えろ!中川政七商店との経営戦略会議が生んだ「幸せなものづくり」 タダフサ
つかい手がそこに魅力を感じ、
製品を正当な価格で買うことができる。
幸せなものづくりとは、きっとそうあるべきだ。
新潟県・三条市の包丁メーカーであるタダフサの三代目曽根忠幸さんは、中川政七商店の中川政七さんと共に新ブランド『庖丁工房タダフサ』を立ち上げた。
想いや技術をつかい手に正しく届ける仕組みを作れば、安価な大量生産をせざるを得ないものづくりの現場の状況は変えられる。
結果として、5年前に比べ、売上を約2倍に伸ばし、今では三条のものづくりを引っ張る存在としての立ち位置を確固たるものにした。
燕三条地域全体へプラスの影響力を伝播させていくことになる、ものづくり企業の挑戦の軌跡。
「ユーザーに判断を任せるのは、何も考えていないのと同じだ!」つくり手の想いをきちんと伝えるものづくりを
「この人に、三条の鍛冶の未来を託そう。」
市の取り組みとして、中川さんに三条の鍛冶屋のコンサルティングをお願いすることになり、対象として名前が上がったのが、タダフサだった。
株式会社タダフサ(以下:タダフサ)は、曽根さんの祖父が1948年に興した会社で、創業約70年の老舗だ。元は大工道具の曲金(まがりかね)を作る腕利き職人だった祖父は、問屋から依頼を受け、独学で包丁作りを始めた。
その後、包丁メーカーとして曽根さんの父へと引き継がれ、年商一億円規模の会社に成長してきた。
一方の中川政七商店は、奈良県で300年以上続いてきた麻織物を扱う老舗。
13代目政七を襲名した中川政七さんは2008年に社長に就任後、巧妙な経営戦略で中川政七商店を全国に33店舗も展開。「日本の工芸を元気にする!」を目標に掲げ、経営に不安を抱えた事業社のコンサルティングを通し、数々のものづくりを蘇らせてきた人物だ。
三条市からの後押しもあり、曽根さんは中川さんと二人三脚で走り始める決心をした。
物が思うようには売れない時代。
取引先に「質を落としてもいいから安くしろ」と要求されることもあったと曽根さんは話す。
「ホームセンターで、自分たちが『とにかく安く』作った包丁が雑に並べられているのを見ると、嫌気が差しました。お客さんに『これでいっか』と消極的な選択をされて、買われていくんですから…。」
そんな状況では、タダフサのつくり手としての想いが消費者まで届いていないことは明らかだった。
実は、中川さんのコンサルティングが始まる直前に、曽根さんは大きな決断をしていた。
当時のタダフサの売上の約1割に当たる、1000万円分の包丁の取り引きを止めたのだ。
この決断は「とにかく安く」という要求に答え続けるものづくりからの脱却を意味していた。
「1000万円の売上があったとしても、ほとんど利益の出ない仕事だったんです。ところが作業量は多くて、社員は残業ばかりしていました。それならば、同じ1000万円の売上で100万円の利益を出せるかもしれない仕事に、時間と労力を確保した方がいいと判断しました。中川さんとやっていく中で、1000万円くらいは穴埋めができると思ったんです。」
曽根さんは、中川さんと「タダフサらしい」ものづくりで勝負することに、工場の未来を懸けた。
しかし、中川さんはこれをはっきりと否定したという。
──本来は、メーカーの方がものづくりについて一番考えているはず。それなのに、判断を最終的にユーザーに委ねてしまうのは、ちゃんと考えていないのと同じだ。世の中に数多ある商品の中からタダフサに関心を向けてくれる人たちに対して、自分たちがどんな想いでものを作っているのかをちゃんと伝えていかなくては。
『庖丁工房タダフサ』の誕生は、つかい手ではなく、意外にもつくり手である自分たちのことを、もう一度じっくり棚卸しするところから始まった。
タダフサが目指したのは、つくり手である自分たちの豊富な専門知識をもとに着想を得て、ユーザーがまだ気づいていない「新しい包丁の魅力」を生み出すという方向性だった。
900種類の包丁から絞り込まれた「基本の3本、次の1本」
あらゆるニーズに応えて、包丁をつくり続けてきた結果、タダフサの包丁のバリエーションは実に900種類にまで及んでいた。
「そんなに種類があっても、売上の80%を担っているのは全体の約20%の商品でした。いくつもある包丁の種類の中には、1年に1本しか売れないものもありました(笑)」
中川さんの指導のもと、思い切ってほとんどの在庫を捨て、受注生産にシフトチェンジすることに。
全く作らないのではなく、めったに注文の来ない包丁は出来上がるまで待ってもらう事で、作業の効率化を図った。
こうして、900種類の包丁の中から、問屋向けに常時生産する商品を70種類に絞った。
「ウチでは、板前さんや漁業関連の人たちが使う刺身包丁や出刃包丁など、専門的な刃物も豊富に作ってきました。ところが、1本の刺身包丁を使い切るのに30年くらいかかるんです。根強いリーピーターさんがいても、次に売れるのは30年後って、かなり先ですよね…(笑)」
そこからさらに一般の消費者向けに7本に絞った包丁で、新ブランド『庖丁工房タダフサ』がスタートした。
三徳包丁・ペティナイフ・パン切り包丁の「基本の3本」を揃え、料理の腕が上がったら、さらにより細かく用途が分かれた4種類の包丁から「次の1本」を選ぶ、といった購買の流れを想定した商品構成だ。
包丁で一番重要なのはもちろん切れ味の良さ。
職人に言わせれば、どんな包丁も研がなければ切れなくなるのは当たり前だ。
しかし、現代の一般家庭では「包丁を研ぐ」といった習慣はあまり根付いていない。おそらく、ステンレス製の研がずに済む包丁が多く流通しているからだろう。
そこで、『庖丁工房タダフサ』ではパッケージにある工夫を凝らすことにした。
つかい手が研ぐことができないなら、つくり手がメンテナンスをすればいい。
購入時のパッケージをそのまま使って、もう一度タダフサの工房に送れるような「通い箱*」の形状にした。
さらに、包丁がどんな状態になれば研ぐタイミングなのかを分かりやすく示すため、「研ぎ頃」という概念をつくり、リーフレットを作成。
これを包丁のパッケージに同封した。
この施策が、タダフサの包丁作りへの想いを伝えることにつながり、消費者も魅力を感じて商品を買ってくれるという「幸せな関係」を生みだした。
タダフサの工場内では、愛用者から届いた包丁が「研ぎ」の工程を待ち、並ぶ姿が日常化した。
パッケージや売り出し方に工夫を加え、消費者が面倒に感じていた「包丁を研ぐ」行為を価値あるサービスに昇華させたことで、『庖丁工房タダフサ』のファンはその後も、順調に増えていった。
「研ぐ」ことに重点を置き、タダフサの想いをつかい手にきちんと届けることで、売上はコンサルティング前の約2倍にまで伸びた。
ものづくりの背景が透けて見えるような商品をつくりたい。かっこいい職人の姿を子どもたちに
曽根さんは、初代実行委員長として「工場の祭典」を指揮。
新潟県の燕三条の名を世間に広める立役者のひとりとなった。
「ウチは、三条にあったからこそ、この産地の恩恵を受けてやってこれた工場です。だから、周囲から『タダフサの一人勝ちだ』なんて思われるのは嫌でした。産地としての燕三条全体をもっと良くしていきたいんです。」
幼い頃から工場や職人を身近に感じて育った曽根さんは、現在の三条のものづくりに危機感を抱いていた。
だから「工場の祭典」では、普段は近づき難い雰囲気の工場をオープンにすることで、ものづくりの背景にある職人たちの姿を活き活きと人々に伝えることを目指したのだ。
ある日、社員のひとりがそれを裏付けるような貴重な証拠を見つけた。
小学生だった曽根さんが書いた卒業文集の中の一節に、
「将来の夢は包丁屋」
と、はっきりと書いてあったという。
「そんなの、自分では全然覚えていなかったんですけどね(笑)確かに、親父とか、じいちゃんの仕事を『かっこいいな』と思っていました。小学校から戻ると工場の事務所に寄るのが日常だったので、働いている姿はよく見ていましたから。」
ところが、三条のものづくりに関わる人全員がそうとは限らない。
曽根さんには、どうしても悔しいことがあった。
「知り合いの包丁職人が、自分の仕事について息子に恥ずかしくて話せない、と言っていたんです。自分の子どもに誇れる仕事でなきゃ、大人として人に夢は語れません。ましてや経営者ともなれば、自分の子どもすら惹きつけられないのに、よそさまの子どもに『一緒に働こう』なんて言えないじゃないですか。それぐらいの気持ちと覚悟を持って仕事をするべきじゃないのかなって思うんです。」
──三条の子供たちの憧れとなるべき仕事にする事。
タダフサには、年間で計7、8校の小学校が工場見学にやってくる。さらに夏休みには、三条市主催のキッザニアとのプログラムで、子どもたちがタダフサの仕事体験をする。
積極的に、子どもたちに働く職人たちの姿を見せていく取り組みだ。
そんな子どもたちに、曽根さんは得意気に「だろー?」と笑いかける。
どんな仕事でも、誇りを持って働く人の姿はかっこいい。
それを子どもたちにしっかり見てもらうことで、かつての曽根少年のように、ものづくりの世界で働くことを夢見る子どもは少なからず出てくるはずだ。
「日本」という産地を世界に残していきたい
中川さんとのつながりで知り合った『大日本市』*のメンバーとの交流から、新たなの使命を見出している。
「三条はまだ国内では恵まれている方で、他の地域には工場が一社でもなくなったら産業全体が傾いてしまう状態のところもあります。だから、これまでお付き合いの無かったような地域からも三条に『こういうのできない?』と相談をもらうようになってきているんです。三条を盛り上げながら、他の地域ともどんどんつながりを作って、日本の産地全体で助け合っていく必要があります。」
「メイドインジャパン」という言葉からも分かるように、世界から見れば、「日本」という国は、ひとくくりの産地。
タダフサの商品も、海外への売上が5年前よりも約5倍にまで伸びている。
メンテナンスをしながら物を長く使う習慣のある欧米人にとって、よく切れるし、研ぎやすいタダフサの包丁は大人気なのだ。
「ドイツに、ゾーリンゲンという刃物の世界的な産地があります。しかし、残念ながら現在は産地としての機能をほぼ崩壊させてしまっている状態です。なぜなら、工場が海外からの出稼ぎ労働者を雇って安くものづくりをし、自分たちの首を自ら締めてしまったから。僕は毎年展示会でドイツに行くんですが、現地の人々は、自分たちの国で失ってしまったものづくりの仕組みが日本には残されていることに気付いていて、『日本が作れなくなっちゃ困る』と言うんです。」
「メイドインジャパン」は、世界の消費者の希望を背負っている。
中川さんのコンサルティング期間が終了した、現在のタダフサの工場で育まれているのは、つくり手の想いまでを詰め込んで、正当な価格で買われる「幸せなものづくり」のかたち。
「かっこいい!」と無邪気に声を上げる子どもたちに、「だろ?」と笑いかける曽根さんの姿は、今や世界のものづくり業界に名を馳せる燕三条の、一番星だ。
ーーー